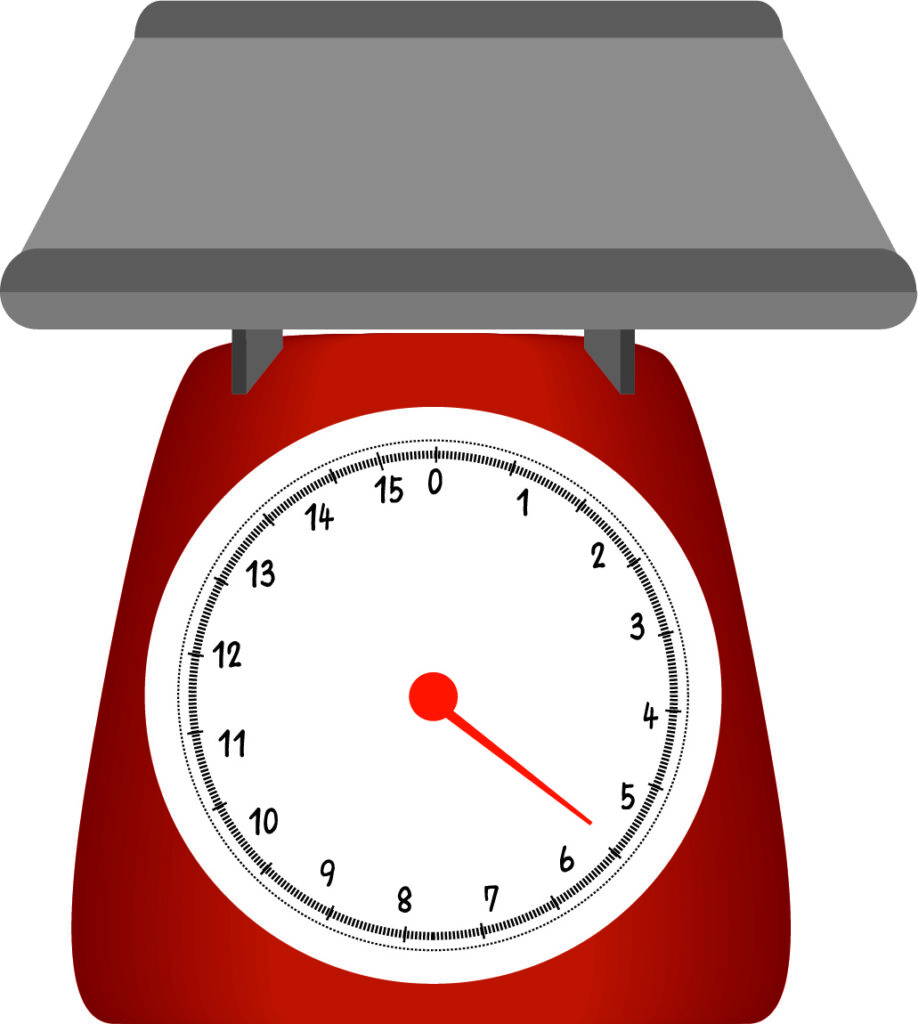トラックの最大積載量は、実は減らしたり増やしたりすることができるのだ。今回はこの「減トン・増トン」について説明していきたい。
そもそもトラックの最大積載量は「車輌総重量-車輌重用-(乗車定員×55kg)」で計算されている。この計算式を元に、その積載量を増やしてより荷物を多く積めるようにしたり、逆に減らしたりすることができるのだ。では、なぜ積載量を変更するのか?その理由に加えて、メリットとデメリットを説明しよう。
まず増トンについて。増トン車は文字どおり最大積載量を4トンから6トン、6トンから8トンなどに増やしたトラックのこと。例えば4トントラックをベースに6トンへ増トンした場合、大型トラックと比べると車輌価格と維持費が安いことや、大型車よりもコンパクトで運転がしやすいと言うメリットが発生する。

しかし、そうしたメリットの反面で標準車輌に比べて税金が高くなるというデメリットもある。また積載量が増えると燃料代も余計にかかることになる。コスト面で見ると一長一短ではあるので、そのあたりのバランスを考えるのは重要なポイントと言えるだろう。
では、逆に減トンはどうだろうか。増トンで積載量を増やす理由はなんとなく想像できるが、逆に減らす意味はどんなところにあるのだろうか。普通に考えれば、最大積載量を少なくするのは不利に思えるが、減トンすることで、自動車税と自賠責保険を安く抑えることができるのだ。
これはトラックの自動車税が最大積載量と比例しているためで、減トンすることで自動車税が下がる。さらにトラックにかける自賠責保険は最大積載量2トンを境に保険料が変わることから、自賠責保険を安くできる可能性が高いのだ。

しかし、減トンした場合は詰める荷物の量が減ってしまうことになる。つまり増トンはたくさん荷物が積めるが維持費が高くなり、減トンはその逆ということになるわけだ。
ではトラックの増トンと減トンはどのような手続きが必要なのだろうか。増トンを行なうには、中型トラックの車軸あるいはフレームを強化して車輌重量を増やし、積載量を6.5トンや8トンまで増やすというやり方があります。2007年に道路交通法が改正されて4トン車の車輌総重量が11トン未満となったことで、増トンが可能になったのだ。
一方で減トンを行うには、タイヤのプライ数(強度)を下げて積載量を下げれば、減トンが可能だ。もちろん、こうした増トンや減トンは正式な手続きを踏めば違法改造でもない。しかし必ず構造変更手続きが必要であるため、それなりの手間や費用がかかるため、気軽に最大積載量を変更するというわけにはいかないのだ。